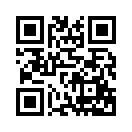2015年06月24日
ジャングルパーチ調査(最終報告)
6月に入り、JP調査もようやく季節が一回りしました(笑)
思い起こせば15年前、沖縄に移住した時に何の気なしに見つけた「オオクチユゴイ」と言う沖縄の清流に棲む魚に興味を持ち、やんばるへ出かけ、偶然釣り上げることができた魚は沖縄の海に棲むトロピカルな雰囲気の魚とは全く異なるものでした。

銀を基調に黒とも茶色とも、また緑とも言えないような色に縁どられた鱗に規則正しくちりばめられた点と、イワナのような唐草模様を頭にまといオレンジのアイシャドウを引いた洗練された装いは、華やかさは控えめながらとても美しく見えました。
その後しばらくは釣りから遠ざかっていましたけど、子供も手を離れ余暇を楽しむ時間も増えるに従い、釣り熱が再燃し始めました。
足繁くフィールドに通うにつれ「悪い友達」(笑)が増え、魚もそれなりに釣れるようになり始めた時、あの頃釣ったオオクチユゴイの迫力あるバイトや、トルクのある引きをもう一度味わいたい衝動に駆られ、やんばる通いが始まりました。
そんな単純な理由で始めたJPフィッシングですが、インターネット上には思いのほかこの魚に関する情報が少なく、
「それならば、とりあえず1年を通して魚を追いかけてみよう」
ということになりました。
幸いこんな突拍子もないことにお付き合いくださる「悪い友達」もすぐに見つかり、気の長い調査が始まったわけです。
思い起こせば15年前、沖縄に移住した時に何の気なしに見つけた「オオクチユゴイ」と言う沖縄の清流に棲む魚に興味を持ち、やんばるへ出かけ、偶然釣り上げることができた魚は沖縄の海に棲むトロピカルな雰囲気の魚とは全く異なるものでした。

銀を基調に黒とも茶色とも、また緑とも言えないような色に縁どられた鱗に規則正しくちりばめられた点と、イワナのような唐草模様を頭にまといオレンジのアイシャドウを引いた洗練された装いは、華やかさは控えめながらとても美しく見えました。
その後しばらくは釣りから遠ざかっていましたけど、子供も手を離れ余暇を楽しむ時間も増えるに従い、釣り熱が再燃し始めました。
足繁くフィールドに通うにつれ「悪い友達」(笑)が増え、魚もそれなりに釣れるようになり始めた時、あの頃釣ったオオクチユゴイの迫力あるバイトや、トルクのある引きをもう一度味わいたい衝動に駆られ、やんばる通いが始まりました。
そんな単純な理由で始めたJPフィッシングですが、インターネット上には思いのほかこの魚に関する情報が少なく、
「それならば、とりあえず1年を通して魚を追いかけてみよう」
ということになりました。
幸いこんな突拍子もないことにお付き合いくださる「悪い友達」もすぐに見つかり、気の長い調査が始まったわけです。
・
最初のころは何も考えなくても簡単に釣れたオオクチユゴイは、季節の終わりとともに反応が悪くなり、冬場になると釣れる河川や場所も限定されてきました。
これは水温と餌となる動物の活動状況に左右されると思われますが、沖縄では周年虫を目にしますので、活性の差はあれ冬場でも積極的に捕食しているものと考えていいと思います。
これまでの調査は先に中間報告(その1・その2)と言う形で妄想していますが、その後新しく気が付いた事として、ある河川では9月ごろに少しやせ気味の個体を見かけ、12月下旬あたりから腹回りの太い個体を見かけるようになりました。

ところが、ほかの河川では3月から5月にはやせた個体を見るようになりました。

実際に生殖器官を調べたわけではありませんので、この時期が産卵期であるかどうかは確証が持てませんが、石垣のriseさんは春産卵を示唆していますし、昨年の冬場には幼魚の群れをたくさん見た河川もありましたから、実際のところは地域や河川によってかなり幅があるのかもしれません。
様々な条件を加味すると、亜熱帯から熱帯の魚に多く見られる周年産卵と考えるほうが妥当なところかもしれません。(魚類の生殖周期と水温等環境条件との関係)
一年を通しておおむね寄り道することなくジャングルパーチを釣り続けることができましたので、最後に簡単なまとめをしてみたいと思います。
今回、一年を通してオオクチユゴイ(ジャングルパーチ)を追いかけてみましたが、周年狙えるターゲットであることがわかりました。
使うルアーの種類はあまり変えずほぼTOPプラグで通しましたが、冬場でも陸生昆虫は多く見ることができましたので充分TOPゲームが成立します。ミノーやスプーン、ワームなどを使えばさらに釣果が上がるかもしれません。
食性は陸生昆虫を中心に水棲昆虫や甲殻類、魚類を捕食し、あまりセレクティブにならないようですのでルアーセレクトは神経質になる必要は無さそうです。
反対にプレゼンテーションはだいぶ神経を使うことが多く、ライナー性のアプローチより山なりのアプローチの方が反応が良く、ルアーの着水波紋も適度に出る方が食いがいいように感じました。
カラーはTOPに限って言えば黄色~緑系、白、枯草色などが良く反応しました。
雨が降ると活性が一気に上がるようですし、早朝や夕暮れであたりが暗い時の方がプレッシャーが少なく釣りやすいようです。
また、風の影響で水面がさざ波立っているときも悪くありません。
沖縄の河川は流程や流水量の割にダムに貯蔵される水量が大きいので、ダムの存在自体が河川の水量や水質、水温に及ぼす影響が強く出るように感じました。
冬場は上流にダムの無い川、もしくは水量の多い川を選ぶとよいと思います。
ただし、一見ダムがなさそうに見えても取水用の堰や砂防ダムなどがありますので、沖縄全体の河川は昔に比べるとかなり水量が少なくなってきているようです。
この影響で河口に砂が溜まり、満潮時以外は河川と海が完全に隔てられてしまうところが少なくありません。
こういった河川にはあまり大型は見られず、個体数も少ないようです。
稚魚が見られる時期や釣り上げた個体のコンディションによって産卵する時期は河川によって大きく変わる事が示唆されましたが、これはあくまで推察であって確証はありません。
海で産卵すると仮定すると、卵の発生には塩水が必要になる事から魚止めになるダムの上流には生息できないと考えていますが今後の検討課題です。
ただし、落差数m程度の滝であれば簡単に遡上でき、かなり上流部にも生息していることを確認できました。
以上が素人なりに考えたオオクチユゴイに関する事柄ですが、結論から言うと食性以外の生態は結局よくわかりませんでした(笑)
ただ、ほかの魚同様、生息域が狭くなりつつあり、昔ほど個体数も多いわけではなさそうですので、できる限りダメージの少ない方法で素早いリリースを心がけたいものです。
バーブレスフックは言うに及ばず、なるべく魚体に触れない方法でキャッチし、やむを得ず魚体を持つときはグローブ越しや川の水に手を付けて少しでも手を冷やしてから触るようにしています。
特に大型の個体は回復に時間がかかるようでしたので、蘇生には十分な時間をかけてあげましょう。
一つの目安として、釣り上げた直後は緊張ですべてのひれが立っていますが、蘇生を行うと背びれを閉じてリラックスします。
水中で魚体を前後に動かし、強制的にえらに水を通して

このタイミングでリリースすると元気に帰っていきます。

国内では、ほぼ沖縄でしか出会えないこの素晴らしい淡水魚をいつまでも後世に残していきたいものです。

最初のころは何も考えなくても簡単に釣れたオオクチユゴイは、季節の終わりとともに反応が悪くなり、冬場になると釣れる河川や場所も限定されてきました。
これは水温と餌となる動物の活動状況に左右されると思われますが、沖縄では周年虫を目にしますので、活性の差はあれ冬場でも積極的に捕食しているものと考えていいと思います。
これまでの調査は先に中間報告(その1・その2)と言う形で妄想していますが、その後新しく気が付いた事として、ある河川では9月ごろに少しやせ気味の個体を見かけ、12月下旬あたりから腹回りの太い個体を見かけるようになりました。

ところが、ほかの河川では3月から5月にはやせた個体を見るようになりました。

実際に生殖器官を調べたわけではありませんので、この時期が産卵期であるかどうかは確証が持てませんが、石垣のriseさんは春産卵を示唆していますし、昨年の冬場には幼魚の群れをたくさん見た河川もありましたから、実際のところは地域や河川によってかなり幅があるのかもしれません。
様々な条件を加味すると、亜熱帯から熱帯の魚に多く見られる周年産卵と考えるほうが妥当なところかもしれません。(魚類の生殖周期と水温等環境条件との関係)
一年を通しておおむね寄り道することなくジャングルパーチを釣り続けることができましたので、最後に簡単なまとめをしてみたいと思います。
今回、一年を通してオオクチユゴイ(ジャングルパーチ)を追いかけてみましたが、周年狙えるターゲットであることがわかりました。
使うルアーの種類はあまり変えずほぼTOPプラグで通しましたが、冬場でも陸生昆虫は多く見ることができましたので充分TOPゲームが成立します。ミノーやスプーン、ワームなどを使えばさらに釣果が上がるかもしれません。
食性は陸生昆虫を中心に水棲昆虫や甲殻類、魚類を捕食し、あまりセレクティブにならないようですのでルアーセレクトは神経質になる必要は無さそうです。
反対にプレゼンテーションはだいぶ神経を使うことが多く、ライナー性のアプローチより山なりのアプローチの方が反応が良く、ルアーの着水波紋も適度に出る方が食いがいいように感じました。
カラーはTOPに限って言えば黄色~緑系、白、枯草色などが良く反応しました。
雨が降ると活性が一気に上がるようですし、早朝や夕暮れであたりが暗い時の方がプレッシャーが少なく釣りやすいようです。
また、風の影響で水面がさざ波立っているときも悪くありません。
沖縄の河川は流程や流水量の割にダムに貯蔵される水量が大きいので、ダムの存在自体が河川の水量や水質、水温に及ぼす影響が強く出るように感じました。
冬場は上流にダムの無い川、もしくは水量の多い川を選ぶとよいと思います。
ただし、一見ダムがなさそうに見えても取水用の堰や砂防ダムなどがありますので、沖縄全体の河川は昔に比べるとかなり水量が少なくなってきているようです。
この影響で河口に砂が溜まり、満潮時以外は河川と海が完全に隔てられてしまうところが少なくありません。
こういった河川にはあまり大型は見られず、個体数も少ないようです。
稚魚が見られる時期や釣り上げた個体のコンディションによって産卵する時期は河川によって大きく変わる事が示唆されましたが、これはあくまで推察であって確証はありません。
海で産卵すると仮定すると、卵の発生には塩水が必要になる事から魚止めになるダムの上流には生息できないと考えていますが今後の検討課題です。
ただし、落差数m程度の滝であれば簡単に遡上でき、かなり上流部にも生息していることを確認できました。
以上が素人なりに考えたオオクチユゴイに関する事柄ですが、結論から言うと食性以外の生態は結局よくわかりませんでした(笑)
ただ、ほかの魚同様、生息域が狭くなりつつあり、昔ほど個体数も多いわけではなさそうですので、できる限りダメージの少ない方法で素早いリリースを心がけたいものです。
バーブレスフックは言うに及ばず、なるべく魚体に触れない方法でキャッチし、やむを得ず魚体を持つときはグローブ越しや川の水に手を付けて少しでも手を冷やしてから触るようにしています。
特に大型の個体は回復に時間がかかるようでしたので、蘇生には十分な時間をかけてあげましょう。
一つの目安として、釣り上げた直後は緊張ですべてのひれが立っていますが、蘇生を行うと背びれを閉じてリラックスします。
水中で魚体を前後に動かし、強制的にえらに水を通して

このタイミングでリリースすると元気に帰っていきます。

国内では、ほぼ沖縄でしか出会えないこの素晴らしい淡水魚をいつまでも後世に残していきたいものです。

この記事へのコメント
ジャングルパーチ博士の称号…
誰かから貰えるはずね!!(≧∇≦)
今度は、Tの研究もお願いしますm(__)mケッコーマジデスw
誰かから貰えるはずね!!(≧∇≦)
今度は、Tの研究もお願いしますm(__)mケッコーマジデスw
Posted by T.T at 2015年06月24日 22:44
at 2015年06月24日 22:44
 at 2015年06月24日 22:44
at 2015年06月24日 22:44Lwing先生のJP講義も楽しく受講させていただきました( ´ ▽ ` )ノ
次回からのJP狙いに大変勉強になりました(^_−)−☆
あとは自分なりにアーバンJPの仕留め方を突き詰めてみたいと思いますm(_ _)m
あっ、本日憧れのあばさ〜殿下とびっちゅうさん、Bトラさんにお会いし少しだけ御一緒させていただきましたよ( ´ ▽ ` )ノ
やっぱ、AJRには悪い人が集まりますね(^_−)−☆www
ノーマルな人間でよかった〜f^_^;)www
次回からのJP狙いに大変勉強になりました(^_−)−☆
あとは自分なりにアーバンJPの仕留め方を突き詰めてみたいと思いますm(_ _)m
あっ、本日憧れのあばさ〜殿下とびっちゅうさん、Bトラさんにお会いし少しだけ御一緒させていただきましたよ( ´ ▽ ` )ノ
やっぱ、AJRには悪い人が集まりますね(^_−)−☆www
ノーマルな人間でよかった〜f^_^;)www
Posted by N野 at 2015年06月25日 00:40
お疲れさまでした(^^)
素晴らしさは伝えたいけど、フィールドは保護(サンクチュアリ化)して守りたい…
開発はして欲しくないけど、地域に住む住人の皆さんの利便性向上を無視する事は出来ない…
難しいんですよね~(^^;)
東シナ海と太平洋側、河川自体の奥行き(懐の深さ)、降雨や湧水などで供給される水質(Ph値)と平均水温…
まだまだ調べて欲しいので、ヤンバルに引っ越して下さい(爆)
素晴らしさは伝えたいけど、フィールドは保護(サンクチュアリ化)して守りたい…
開発はして欲しくないけど、地域に住む住人の皆さんの利便性向上を無視する事は出来ない…
難しいんですよね~(^^;)
東シナ海と太平洋側、河川自体の奥行き(懐の深さ)、降雨や湧水などで供給される水質(Ph値)と平均水温…
まだまだ調べて欲しいので、ヤンバルに引っ越して下さい(爆)
Posted by Lee@AK47 at 2015年06月25日 12:41
私もリリースする魚体に触れる時は手を濡らしたりグローブしたりしています。
川の魚ならなお更それが大事になってくるのでしょうね。
いつまでも沖縄の自然が残るといいですね。
悪い友達もLwingさんのこと超悪いって思ってるはず!
川の魚ならなお更それが大事になってくるのでしょうね。
いつまでも沖縄の自然が残るといいですね。
悪い友達もLwingさんのこと超悪いって思ってるはず!
Posted by 空飛ぶさくら at 2015年06月25日 19:47
at 2015年06月25日 19:47
 at 2015年06月25日 19:47
at 2015年06月25日 19:47勉強になりました^ ^
自分も出来るだけダメージの少ないリリース心がけます!
あと、ダムや広い池だと海と勘違いして産卵するって聞いた事あります。なので上流のダムや池の調査もお願いします(笑)
自分も出来るだけダメージの少ないリリース心がけます!
あと、ダムや広い池だと海と勘違いして産卵するって聞いた事あります。なので上流のダムや池の調査もお願いします(笑)
Posted by にんじんさん at 2015年06月25日 23:10
食性意外は謎 笑
ですが魅せてくれる魚には間違いないですね 笑
ですが魅せてくれる魚には間違いないですね 笑
Posted by TOPTROOPER at 2015年06月26日 03:06
沖縄のとあるダムのリュウキュウアユは、ダムを海と勘違いして繁殖してるみたいですね。
>水中で魚体を前後に動かし、強制的にえらに水を通して
これ、効果ありますね。(笑
リリース後、稀にミキイユがひっくり返ったまんまのときにフィッシュグリップで摘んでやってます。
1.7kmもコンクリート三面張り(水深2、3cm)が続く川の上流域で、ミキイユの群れを見かけた。
上流域はわりと水深もあり、渓流っぽいが…海と行き来できるのか?
今は謎。
>水中で魚体を前後に動かし、強制的にえらに水を通して
これ、効果ありますね。(笑
リリース後、稀にミキイユがひっくり返ったまんまのときにフィッシュグリップで摘んでやってます。
1.7kmもコンクリート三面張り(水深2、3cm)が続く川の上流域で、ミキイユの群れを見かけた。
上流域はわりと水深もあり、渓流っぽいが…海と行き来できるのか?
今は謎。
Posted by 新兵衛 at 2015年06月26日 07:37
小河川の河口埋まりは、ほんとに影響しますね。無駄な道路工事をやめて、河口のしゅんせつをしてもらいたいです。
つぎは、オオクチユゴイとクチビル姐さんの関係をつきとめてください(笑)
つぎは、オオクチユゴイとクチビル姐さんの関係をつきとめてください(笑)
Posted by rise at 2015年06月26日 08:26
T.Tさん、
ちょうだい(爆)
Tはチヌが片付いてから考えます(笑)
ちょうだい(爆)
Tはチヌが片付いてから考えます(笑)
Posted by Lwing at 2015年06月26日 08:34
at 2015年06月26日 08:34
 at 2015年06月26日 08:34
at 2015年06月26日 08:34N野さん、
妄想だらけで参考にはならないと思います^^;
都会のJPは、また違った習性があるかもしれませんね。
結構な確率でテラピアと混生していますから、この辺の関係がどう影響してくるか観察する必要がありそうです。
妄想だらけで参考にはならないと思います^^;
都会のJPは、また違った習性があるかもしれませんね。
結構な確率でテラピアと混生していますから、この辺の関係がどう影響してくるか観察する必要がありそうです。
Posted by Lwing at 2015年06月26日 08:39
at 2015年06月26日 08:39
 at 2015年06月26日 08:39
at 2015年06月26日 08:39Lee@AK47さん、
おっしゃる通り悩ましいところです。
ダムのおかげで断水や洪水はなくなり生活に不便はなくなりましたけど、やはり環境負荷はあります。
特に、オオクチユゴイの研究がされていない理由は漁業資源としての価値がないからで、ダムがJPの生態に及ぼす影響を考える人は皆無でしょう。
10年後にはやんばるに引っ越す予定ですので以後の調査はそれまでお待ちください(笑)
おっしゃる通り悩ましいところです。
ダムのおかげで断水や洪水はなくなり生活に不便はなくなりましたけど、やはり環境負荷はあります。
特に、オオクチユゴイの研究がされていない理由は漁業資源としての価値がないからで、ダムがJPの生態に及ぼす影響を考える人は皆無でしょう。
10年後にはやんばるに引っ越す予定ですので以後の調査はそれまでお待ちください(笑)
Posted by Lwing at 2015年06月26日 08:57
at 2015年06月26日 08:57
 at 2015年06月26日 08:57
at 2015年06月26日 08:57空飛ぶさくらさん、
偉そうに書いてしまいましたけど、できる範囲でしかできませんし、突き詰めればただの自己満足なんですけどね^^;
さくらさんの友達も、きっと、さくらさんを悪い友達って思っているはず(笑)
偉そうに書いてしまいましたけど、できる範囲でしかできませんし、突き詰めればただの自己満足なんですけどね^^;
さくらさんの友達も、きっと、さくらさんを悪い友達って思っているはず(笑)
Posted by Lwing at 2015年06月26日 09:06
at 2015年06月26日 09:06
 at 2015年06月26日 09:06
at 2015年06月26日 09:06にんじんさん、
アユや鱒などは河川で産卵した後、稚魚が海へ降りますのでダムなどで閉鎖された純淡水環境でも世代をつなぐ可能性はあるのですが、汽水域もしくは海水域で産卵する魚は、ダム湖で産卵しても孵化は難しそうです。
もし、ダムの上流でJPが世代をつないでいるとしたら、産卵は海ではない、もしくは塩川のように塩水が湧き出ている可能性が出てきますね^^)
アユや鱒などは河川で産卵した後、稚魚が海へ降りますのでダムなどで閉鎖された純淡水環境でも世代をつなぐ可能性はあるのですが、汽水域もしくは海水域で産卵する魚は、ダム湖で産卵しても孵化は難しそうです。
もし、ダムの上流でJPが世代をつないでいるとしたら、産卵は海ではない、もしくは塩川のように塩水が湧き出ている可能性が出てきますね^^)
Posted by Lwing at 2015年06月26日 09:17
at 2015年06月26日 09:17
 at 2015年06月26日 09:17
at 2015年06月26日 09:17TOPTROOPERさん、
所詮素人調査なのでこんなものです(笑)
それでも充分魅力的な魚です(*´Д`*)
所詮素人調査なのでこんなものです(笑)
それでも充分魅力的な魚です(*´Д`*)
Posted by Lwing at 2015年06月26日 09:29
at 2015年06月26日 09:29
 at 2015年06月26日 09:29
at 2015年06月26日 09:29新兵衛さん、
ミキイユは意外とたくましいところもあり、水深2、3cmのところを這いながら上がっていく姿を何度か確認しています。
普段は雨などで水量が増したところで海との行き来をしているんでしょうね^^)
ミキイユは意外とたくましいところもあり、水深2、3cmのところを這いながら上がっていく姿を何度か確認しています。
普段は雨などで水量が増したところで海との行き来をしているんでしょうね^^)
Posted by Lwing at 2015年06月26日 12:45
at 2015年06月26日 12:45
 at 2015年06月26日 12:45
at 2015年06月26日 12:45riseさん、
沖縄本島では15年前と今とではかなり状況も変わってしまったようで、小規模河川は大潮の満潮以外川とつながらないんじゃないかと思うほど河口が埋まってしまっています。
生活用水や農業用水のために取水しますので水量減少は仕方のないことではありますが。
おそらく、これによって水が停滞するとテラピアが増えてくるのかもしれません^^;
沖縄本島では15年前と今とではかなり状況も変わってしまったようで、小規模河川は大潮の満潮以外川とつながらないんじゃないかと思うほど河口が埋まってしまっています。
生活用水や農業用水のために取水しますので水量減少は仕方のないことではありますが。
おそらく、これによって水が停滞するとテラピアが増えてくるのかもしれません^^;
Posted by Lwing at 2015年06月26日 12:56
at 2015年06月26日 12:56
 at 2015年06月26日 12:56
at 2015年06月26日 12:56因みに飼育下で5センチ位の稚魚が一年で20cm程に成長しています。
飼育下と天然では成長速度に差があると思いますが、思いの外成長は早い魚ではないでしょうか?
そこから推測するに2年程で成熟するのでは?
群れで飼育して産卵までさせてみたいですね。
飼育下と天然では成長速度に差があると思いますが、思いの外成長は早い魚ではないでしょうか?
そこから推測するに2年程で成熟するのでは?
群れで飼育して産卵までさせてみたいですね。
Posted by ぼびぃ at 2015年06月28日 13:51
at 2015年06月28日 13:51
 at 2015年06月28日 13:51
at 2015年06月28日 13:51ぼびぃさん、
私も概ねそう思います。1年で10から15センチ、2年で20から25センチ位と予想いています。
釣りやすいのが25センチ位までなのは、そういう理由なのかと。
そこからは少し成長スピードが落ちてくるのでしょうね
私も概ねそう思います。1年で10から15センチ、2年で20から25センチ位と予想いています。
釣りやすいのが25センチ位までなのは、そういう理由なのかと。
そこからは少し成長スピードが落ちてくるのでしょうね
Posted by Lwing at 2015年06月28日 22:34
えっ!デカすぎです!!。
デカチヌおめでとうございます♪。
このサイズをトップで釣ったらどうなってたんでしょう。。。「笑
スプーンでチヌって釣れるんだ!、
次はトップで釣るの楽しみにしてます!!!!。
デカチヌおめでとうございます♪。
このサイズをトップで釣ったらどうなってたんでしょう。。。「笑
スプーンでチヌって釣れるんだ!、
次はトップで釣るの楽しみにしてます!!!!。
Posted by FD at 2015年07月15日 21:49
at 2015年07月15日 21:49
 at 2015年07月15日 21:49
at 2015年07月15日 21:49あっ!送るところ間違えました。すみません↓
Posted by FD at 2015年07月15日 21:50
at 2015年07月15日 21:50
 at 2015年07月15日 21:50
at 2015年07月15日 21:50